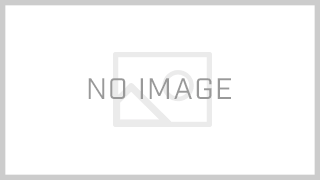2015年9月7日にネットに公開された「今週の必読」シリーズの辻村深月の読書感想文を読んだ。その感想を記す。なお,これは米澤穂信著『王とサーカス』の感想である。
【本文】
優れたミステリを紹介するとき,いつも言葉に迷う。本音を言えば,未読の相手にはなるべく話の詳細を明かしたくない。『王とサーカス』という作品を前にして,今日は特にそう感じる。
舞台は,2001年のネパール。皇太子が国王を始めとする多数の王族を王宮で殺害したとされる衝撃的な事件が現実に起こった,あの年だ。フリーの記者である二十八歳の大刀洗万智は,滞在中に事件の報に接し,取材を開始する。滞在する宿の女主人の知人が事件当夜の王宮で警備にあたっていたと聞き,スクープの予感に胸躍らせながら彼に会いたいと望む。しかし,念願叶って会うことができたラジェスワル准尉の態度は硬い。
「私はこの国を,王の死を,サーカスの演し物にするつもりはない」
若い記者である大刀洗の心は揺れる。報道することとは,書くこととは,記者の使命感とは何なのか。自分は何のために,この国で何をしようとしているのか。
そこに現れる,一体の死体。王を失うという混乱の最中,大刀洗が遭遇したその遺体は,上半身を裸にされ,背中に「密告者」の文字があった――。
主人公大刀洗万智は,米澤穂信の著作『さよなら妖精』に登場した人物だ。ユーゴスラヴィアという遠い国の抱える事情が日本に住む高校生の日常と地続きになる瞬間を描いたこの小説は,主人公が大きな世界と社会というものの前に打ちひしがれる圧倒的な青春小説だった。遠い国で戦う誰かの苦しみを自分に惹きつけ,苦悩する青春の張り裂けんばかりの痛みが,そこには描かれている。
しかし,今,青春時代を抜けた大刀洗は,感傷と無縁だ。自分が対峙している現実を圧倒的な現実としてありのまま受け止め,そこに自分の物語を重ねてみるようなことはしない。なんという大人のミステリ。青春を排除しても,米澤穂信という作家はこんなに強い。
史実を物語に取り込むと,おそらく,その作品は社会性を得た,と評価されがちだ。しかし,優れたミステリは,どれも,多かれ少なかれ,常にその中に社会性を内包してきたはずで,米澤作品もその例外ではない。
戦争や政治,大きな問題を背景に,いつでも事件は起こる。一人の被害者に対し,一人の加害者が抱えた事情や思いは,それがどれだけ小さく個人的なものであったとしても,彼らが属する社会そのものだ。歴史的大事件を背景にしながら,ミステリ作家・米澤穂信があくまで一つの遺体を通じて謎を追う凄さを,ラストまで読者に堪能していただきたい。
【感想】
・前半は物語の中で描かれる事実が淡々と記されている。一方,後半はそれらの事実から導かれる普遍的な解釈,作者の登場人物に対する思いなどが書かれている。シンプルながら強力な文章構成であると感じる。
・ユダヤ人の哲学者ハンナ・アーレントは,良い理解について「注意深く観察し,抵抗すること」と定義した。作中,大刀洗は悩む。自分が,この国の惨事を,日本語で日本で報道する意味は何か,報道することでどのようなことに資するのか。そうした理解することの苦悩をドラマチックに描いている。そのシーンは,苦しい空気を漂わせている一方,とても美しい。
・どの時代においても,答えがある問題は少ない。むしろ,ないことの方が普通だ。けれども,我々はない頭を回転させて,決断していかなければならない。その決断の示唆となるような一冊であると,この感想を読んで感じた。